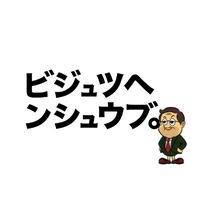Hiroshi Sugimoto:サステイナビリティを考えるとき、もっと大きな時間軸・視点で考えるべきだ。 - Sustainable Japan by The Japan Times
杉本博司 1948年東京生まれ。立教大学卒業後渡米、ロサンジェルスのアートセンター・カレッジ・オブ・デザイン卒業後、74年ニューヨークで作家活動開始。現代美術作家として、世界各地の美術館で個展を開催。2009年建築設計事務所「新素材研究所」を東京に開設。同年、高松宮殿下記念世界文化賞、10年、紫綬褒章。17 年文化功労者。同年、自らの財団である小田原文化財団を設立。 神奈川県小田原市にある江之浦測候所。その名のとおりに受け取れば、気象観測を行う施設となるが、その実は少し違う。 10年ちょっと前、ここはこの地区にはよくある、太平洋を臨むミカン畑でしかなかった。 そこにいくつかの建築物や能舞台が作られ、庭が整えられ、現在では、完全予約制の美術・建築鑑賞施設となっている。 The glass stage with amphitheater seating. The auditorium is a full-size re-creation of a ruined Roman amphitheater in Ferento in the Lazio region of Italy. 設計をしたのは現代美術作家の杉本博司だ。ここを測候所と名付けたのは、冬至、春分、夏至、秋分などを、原始的な手法で観測や体感する機能を備えていることからである。 たとえば、長さ70mのトンネルには1年に1度、冬至の日の出のとき、海から上る太陽の光が真っ直ぐに差し込む。冬至は、死と再生を象徴する日として、世界中の様々な宗教・文化の中で昔から特別な日として認識されてきた。 日々、日が昇り、日が沈む。地球は太陽の周りを少しずつ移動しながら1年をかけてもとに戻る。季節が巡ること。それを観測したとき、人間は自分たちも自然の一部だと悟り、同時に意識が芽ばえ、1日、あるいは1年に営むべきことを自覚する。 狩猟や農業にそれを役立てるのだ。 「早晩、いずれ文明は終わるだろう。そのあと、この場所が遺跡として、いかに美しく残るかである」 自分の設計した建築物が古代遺跡のようになることへの憧れ。そんな思いを抱きながら建物を構想する建築家がほかにいるだろうか。 杉本が建築を設計するときに、他の建築家と異なる点がある。それは通常、建築物は竣工時がいちばん美しく、少しずつ古び、劣化していくものであるが、杉本は時間が経つにつれ、存在感を増すものをつくりたいと考えている。 このように独自の建築を手掛け、ときに人形浄瑠璃や能など、日本の伝統的な芸能の演出もする杉本は、1970年代後半、写真作品によって、芸術家としてデビュー。「写真を美術の表現手段にまで高めたアーティストの一人」として、美術史に足跡を残した。 なかでも画面の上半分は空、真ん中に水平線、下半分は海という構図で撮影される「海景」シリーズは、杉本の代表作の一つで、世界中の海で、この作品を撮影してきた。 「古代の人々と我々は同じものを見ることは可能か」という自問自答がこの作品を生むきっかけになったのだと語っている。1枚の写真の中に悠久の時間を込める。それが杉本の仕事である。 「普通は自分の人生を基準にものを考えるので、10年とか20年という尺度になりがちかと思いますが、たとえばもっともっと長くとか、様々な時間スケールで考えることが大切です。地球の時間軸から見れば、人類の出現から現在まで、ほんの瞬間に過ぎない。あるいは人類出現以降の氷河期の周期を思えば、暑くなると疫病が流行り、寒くなることで生き延びている。サスティナブルを考える際にも、そういう大きな時間の尺度、視点で考えるべきでしょう」 杉本博司の代表作のひとつ「海景」。古代人が見ていただろう風景を、杉本の写真を通じて私たちも目にするという、タイムトラベルを誘う作品だ。 展示室の全長は100m。一直線のギャラリーの先は、夏至の日の出の軸線に向かっている。 人は普通、人生を大きく超える、何百年、何千年あるいはそれ以上の長い時間を、実感として認識するのは難しい。しかし、杉本がそういう見方を美術作品や建築の形にして見せてくれることで、私たちは古代の人々と共有するものを持ち、天体の動きに従う、人類の永々とした営みを感じることができる。それが杉本作品を鑑賞する喜びでもある。 杉本はどのようにして、時間の尺度を自在に変える術を体得したのだろうか。 「少年時代、天体望遠鏡を買ってもらったので星空を観察しました。惑星をよく見ました。昭和30年代は東京でも星が見えたんです。それと、鉄道模型に熱中した時代がありました。鉄道を配したジオラマを作り、それで現実世界を追認したり、理解していくようなところがありました。逆に現実では幻視が襲ってくるような感覚があります」 ジオラマに没入することと実際の世界との照らし合わせ。それによって、自分の位置を知り、どういう環境の中にいるのかも知ることができる。それを体現できる場所として実現させたのが、江之浦測候所というわけである。 江之浦測候所を含む、この相模湾に面した丘陵地を杉本は「柑橘山」と名付け、周辺の農地の存続と整備のため、2011年、農業法人「植物と人間」を設立した。近隣では後継者不足のため、耕作放棄地が広がっていた。かつてこの地を訪れたドイツ人の建築家、都市計画家のブルーノ・タウトはここを「東洋のリビエラ」と呼んだ。それほどの景勝地が荒れ果ててしまうのは忍びないと杉本は考えたのだ。 ここでも杉本の自在な時間の尺度が役に立っている。農業法人「植物と人間」は、人類が生まれてから今日までの植物と人間の関わり方をあらためて認識し直し、これから先も持続可能な植物と人間の共生を維持することを使命としている。この20年〜30年の間、耕作放棄地になり、蜜柑が成って、落ちていく。木の世話をするボランティアの人たちも高齢化していった。 農業法人「植物と人間」代表の磯崎洋才氏。建築家として、江之浦測候所の設計も担当した。 そんなこともあり、農業法人を設立する必然が生まれた。具体的にここで行われるのは、20あまりの種類が穫れる柑橘類の農薬不使用栽培、農業を活用した自然体験イベント、農地活用の研究や整備開発、農業の人材育成や教育事業である。また、柑橘山敷地内に農薬不使用栽培の柑橘類を使用したドリンクやフードを提供するカフェをオープンする予定があり、フードロス対策の実験、実践の場として活用される。 また、昭和20年終戦のときの食糧難や、天変地異による不作や輸送障害を思うと最低限、自分の食べものは自分で作らなければならないときが来るかもしれない。そのときに備えなければならないとも、杉本は考えたのだという。 太陽が今、一年のうちの、どの季節であるかを指し示してくれる。遠く海をのぞみ、足元の畑にはさまざまな作物が成っている。そんな場所に身を置けば誰でも、自分は自然とともにある、自然の中で生かされていると実感できるだろう。 Click […]
sustainable.japantimes.com